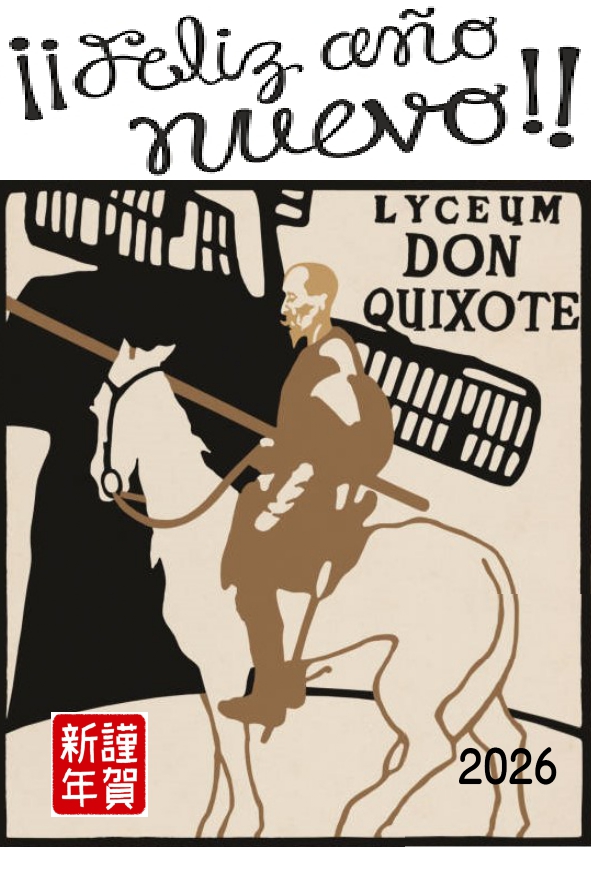2026年1発目の『洋楽の棚』傑作選に選んだ曲は、プロコハルムの「A Whiter Shade of Pale 」です(日本では、多くの洋画に付けられた邦題のタイトルと同様「青い影」というヘンテコなものになってますね・笑)。この曲の歌詞も難解なものとして有名ですが、その難解レベルは最強級。なので、今回の解説も、とてもとても長いですよ(笑)。
【第60回】A Whiter Shade of Pale / Procol Harum (1967)
今回紹介させていただくのは、全世界で1千万枚以上ものシングル・レコードが売れたというProcol Harum の名曲、A Whiter Shade of Pale です。と言っても60年近くも前のヒット曲なので、若い方の多くはご存知ないかもですね(汗)。Procol Harum というなんだか奇妙な名前のこのバンド、Gary Brooker というロンドン出身のミュージシャンが1967年に英国のエセックス州サウスエンドで結成したグループで、A Whiter Shade of Pale の曲の歌詞を書いたKeith Reid はバンドの正式メンバーであるものの、歌も歌わないし楽器も演奏しないという風変わりなバンドでもありました。因みに、Procol Harum というバンド名はこのKeith Reid の友人が飼っていた猫の名前で、ラテン語でaway やat distance を意味するprocul の綴りが間違って伝わったもののようです(Harum はラテン語ではなく、意味は分かりませんけど響きはどこかアラビア語風ですね)。A Whiter Shade of Pale は、メンバーの一人Matthew Fisher(この曲の著作権は自分にもあると後に裁判を起こし、認められた人です)の演奏によるハモンド・オルガン(電子オルガンの一種)の音色のイントロを一度でも耳にすれば二度と忘れることはないという曲ですが、その哀愁を帯びた分かり易いメロディーラインに対して歌詞が非常に難解であることは有名で(難解と言うよりもほぼ理解不能です・汗)、それ故にイーグルスのホテル・カリフォルニアやツェッぺリンの天国への階段と同様、古今東西の先人たちによってこの曲の歌詞に対する様々な解釈が為されてきました。タイタニック号の沈没を暗示しているとか、酒やドラッグによって得られた幻想の世界だとか、男が処女を口説いてモノにする話だとか、パーティーでドラッグをやり過ぎて死んだ少女の話だとか、この曲を聴いた人の歌詞の解釈はまさしく十人十色。ある意味、滅茶苦茶な解釈だらけとも言えますが、A Whiter Shade of Pale の歌詞を書いたKeith Reid(2023年に死去されました)はこの歌詞の意味を直接的に言及したことは無いものの、歌詞を理解するのに役立つ数多くのヒントを残しているので、今回はそれらのヒントを参考にしながら和訳に挑戦してみました。Keith が生前に語っていた主なヒントには以下のようなものがあります。
① I feel with songs that you’re given a piece of the puzzle, the inspiration or whatever. In this case, I had that title, ‘Whiter Shade of Pale,’ and I thought, There’s a song here. And it’s making up the puzzle that fits the piece you’ve got. You fill out the picture, you find the rest of the picture that that piece fits into. つまり、この曲は「Whiter Shade of Pale」というタイトルが先ずありきで、そのタイトルに合わせてパズルを組み合わせるように歌詞を作ったということですね。僕も小説を書く時、先ず最初にタイトルが決まり、それに合わせてストーリーが頭に浮かんでくるということはしばしばあることなので、彼の言わんとしていることは良く分かります。
② では、そのA whiter shade of pale というタイトルがどこから来たのかというと、Keith はI overheard someone at the party saying to a woman, “You’ve turned a whiter shade of pale”, and the phrase stuck in my mind. パーティーで誰かが女性に向かって「You’ve turned a whiter shade of pale 君、蒼い顔がさらに白くなってるよ」と言っているのを聞いて、その言葉が頭から離れなくなったと語っています。普通は単にOh,You’ve turned pale. Are you alright?と言うくらいでしょうから、確かに面白い表現ではありますね。
③ I might have been smoking when I conceived it, but not when I wrote it. It was influenced by books, not drugs. この歌詞を書いた時はタバコは吸ってたかもしれないけど、歌詞はドラッグの影響を受けたものではなく、本に影響されたものだとKeith が自ら語っているように、酒やドラッグにこの歌詞の解釈を求めるというのは誤ったアプローチのようです。
④ I wrote this song to describe a very simple story of a boy who falls too hard for a girl he barely knows and is then rejected by that girl. Nothing more and nothing less. これはもう答えそのものですね。少年がまだ良く分かり合えていない少女にフラれたというストーリーがこの曲の歌詞の軸になっていることは間違いないでしょう。Nothing more and nothing less の言葉どおり、それがこの歌詞の真実なのだと思います。
以上のことを参考にしながら日本語に置き換えたのが以下の歌詞です。先ずはご一読ください。各節の詳細に関しては解説欄にて。
We skipped the light fandango
Turned cartwheels ‘cross the floor
I was feeling kinda seasick
But the crowd called out for more
The room was humming harder
As the ceiling flew away
When we called out for another drink
The waiter brought a tray
僕らはさ、スローなダンスはすっ飛ばして
ダンスフロアで激しく踊ってたんだ
船酔いみたいに僕の頭はクラクラしたけど
周りの連中はもっと踊れって声を張り上げてたよ
部屋の中はますます騒めき立ってさ
天井が吹っ飛ぶ勢いだった
そんな中、僕たちが酒のお代わりを頼むと
給仕がトレイで運んできたんだよな
And so it was that later
As the miller told his tale
That her face, at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale
そう、それはそのあとのことさ
食わせ者が耳打ちしたら
最初は幽霊みたいだった彼女の顔が
もっと蒼白くなったんだ
She said, there is no reason
And the truth is plain to see
But I wandered through my playing cards
And would not let her be
One of sixteen vestal virgins
Who were leaving for the coast
And although my eyes were open
They might have just as well’ve been closed
彼女は言ったよ、理由なんてないし
言うまでもないでしょって
だけど、僕はどうすべきか悩んだね
だって、彼女にはなって欲しくなかったんだ
浜辺へと向かう
16歳のウェスターの巫女の一人なんかにさ
僕は目を見開いてたんだけど
閉じてたのと同じだったのかもしれないな
And so it was that later
As the miller told his tale
That her face at first just ghostly
Turned a whiter shade of pale
そう、それはそのあとのことさ
食わせ者が耳打ちしたら
最初は幽霊みたいだった彼女の顔が
もっと蒼白くなったんだ
A Whiter Shade of Pale Lyrics as written by Keith Reid, Gary Brooker, Matthew Fisher
Lyrics © Onward Music Limited
【解説】
さてさて、A Whiter Shade of Pale の歌詞、如何でしたか?最初の節ではまだなんとなく場所やそこにいる人たちの雰囲気が伝わって来ますが、コーラスのあとの次の節、特にその後半部分は何を言いたいのか良く分からないというのが正直なところです。実はこの曲の歌詞、当初書かれたオリジナルの歌詞は4節で構成されており、さらに意味不明な二つの節がこの後に続いてまして(コンサートではこれらの節を含めたロング・バージョンが歌われることもあったようです)特に第3節はAnd so it was that later で始まるコーラス部分の歌詞を解読する上で重要という気がしましたので、先に残りの歌詞を読んでいただき、それから解説に入りたいと思います。
She said, ‘I’m home on shore leave,’
Though in truth we were at sea
So I took her by the looking glass
And forced her to agree
Saying, ‘You must be the mermaid
Who took Neptune for a ride.’
But she smiled at me so sadly
That my anger straightway died
彼女は言ったよ「休暇でうちに戻った」ってね
ほんとは僕も彼女も海にいたんだけどさ
だから僕は彼女を鏡の傍へと連れて行って
認めさせようとしたんだ
こんな風に言ってね「君は人魚に違いないんだ
海の神を欺いたね」って
でも、彼女は悲しそうに微笑んだだけで
僕の怒りは直ぐに消えちまったよ
If music be the food of love
Then laughter is its queen
And likewise if behind is in front
Then dirt in truth is clean
My mouth by then like cardboard
Seemed to slip straight through my head
So we crash-dived straightway quickly
And attacked the ocean bed
もし音楽が愛の糧なら
笑いはその女王さ
同じように後ろが前なら
ほんとの汚れもきれいなものだよね
名ばかりの僕の口は
頭の中を通り抜けて行くみたいだった
だから僕たちは直ぐに海に潜って
海底を襲ったんだ
それでは、各節の歌詞を紐解いていきましょう。歌詞が難解とされる曲でしばしば見受けられることですが、この曲も出だしからいきなりぶちかましてきます(笑)。第1節1行目のthe light fandango がそれですね。この聞き慣れない単語、ネイティブ話者であっても、それがいったい何であるのか分かる人はほぼ皆無ではないでしょうか。スペインのフラメンコの知識がある人であれば「それってフラメンコの踊りのひとつですよ」と言うかもしれませんが、僕の頭に浮かんだのはポルトガルのフォークダンスであるfandangoでした。ポルトガルでfandango と呼ばれているダンスは、男女のペアが向き合ってステップを踏みながら踊るもので、そのことから僕はこの歌詞のfandango は親密な男女が踊るチークダンスのようなものの言い換えだと考えました(現代フラメンコのfandango は通常、男女がペアになって踊るようなことはありませんし、正式名称はfandangos de Huelva ウエルバ(スペインの地名)のファンダンゴと言って、民俗舞踊のfandango とは異なります)。ここでのlight はslow の意味で使われているような気がしましたので、the light fandango はslow dance cheek to cheek のようなものであり、第1節の舞台となっている場所はダンス・パーティーの会場か街のディスコというのが僕の結論です。Keith Reid がfandango という言葉をどこでどのように知ったのかは分かりませんが、モーツァルトのオペラ「フィガロの結婚(舞台設定はスペイン南部)」を彼が観ていたとすれば、第3幕のフィナーレで、フィガロとスザンナが着飾った村人たちの前でfandangoを踊る姿のようなものを意識してたのかもしれませんね。
2行目のturn cartwheels ‘cross the floor もこれまた良く分からない表現です。turn cartwheels という言葉を聞いて思い浮かぶのは、曲芸師がする横転のようなアクロバティックな動きですが、パーティー会場やディスコで横転しまくる男女なんてのはまずいませんので(いたら迷惑ですよね・笑)「まるで横転でもするかのような激しいダンス」と僕は受け止めました。酒の入った身体で余りにも激しく踊ったのでI was feeling kinda seasick になったと考えれば話の辻褄も合います。4行目のBut the crowd called out for moreから6行目のAs the ceiling flew away までのフレーズは、パーティー会場が非常に盛り上がっていることを想像させ、As the ceiling flew away は勿論、実際に天井が吹っ飛んだ訳ではなく、それくらい盛り上がっていたということの比喩でしょう。7行目のWhen we called out for another drink は、ますます場が盛り上がってきたので、ダンスを踊っていた男女のカップルはもっと盛り上がろうと酒のお代わりを頼んだってな感じでしょうか。最後のThe waiter brought a tray は、トレイを運んできたのではなくa tray with drinks かdrinks on tray と考えるのが自然です。
次にコーラス部分である第2節の2行目、この曲の歌詞の中でも最大の謎のひとつになっているAs the miller told his tale は、多くの先人たちがチョーサーの小説「カンタベリー物語The Canterbury Tales」の中の「粉屋の話The Miller’s Tale」と結びつけて解釈しようとしてきましたが、Keith Reid は音楽雑誌のインタビューに対してI’d never read The Miller’s Tale in my life. Maybe that’s something that I knew subconsciously, but it certainly wasn’t a conscious idea for me to quote from Chaucer, no way と語っています。彼は生前、これと同じようなことを何度も繰り返し言ってましたので、ここは彼の言葉を信じることにしましょう。では、このthe miller というのは一体何者なのか?miller をmirror と解釈する人も多いようで、そんな一人がインタビューでKeith にI always heard the line “the Miller told his tale” as “the mirror told his tale.” I was thinking she was looking in the mirror, something was happening と自説をぶつけていましたが、Keith はYes. That might have been a good idea と答えて笑い飛ばしていました。なので、この線もなさそうです。この他にも、作家のHenry Miller と結びつけて解釈しようとする人たちもいたりしますが、僕は冒頭に記したKeith のヒント①から、As the miller told his tale というフレーズからこの節の解釈をするのではなく、なぜ彼女はさらに蒼白くなったのかの理由を考察すればこの節の答えは見つかると考えました。そもそも、the miller ってのは何を指しているのでしょう?mill が「臼などで粉にする、製粉する」という動詞であるとおり、miller は水車や風車の動力を使って石臼でそれをする人、つまりは製粉職人、粉挽き職人のことです。現代では機械が自動的に製粉をするのでほとんど見かけることはありませんが、中世のヨーロッパでは各地にmiller がいました。農民やパン屋が穀物をmiller の所へ持って行って粉にしてもらう訳です。その際、miller は定められた量の穀物を水車や風車の使用料として徴収し、それがmiller の稼ぎとなっていましたが、定められた以上の量の穀物を徴収する(要はくすねるということ)miller も多かったようで、millerに穀物をくすねられたと訴える記録がヨーロッパ各地に大量に残っています。なぜ僕がここでそんなことについて書いたかというと、miller という言葉の響きを聞いた時、ヨーロッパの人はどのような人物を想像するのだろうかと考えたからで、文献を調べてみると、中世の農民や市民たちはmiller は前述のように穀物の量をちょろまかしていると考える人が多く、そのイメージは「嘘つき、不誠実、穀物泥棒、嫌われ者」といったものであったことが分かりました。次に考えたのは、人の顔が蒼ざめるのはどういう時かという点で、普通、人の顔が蒼ざめる、即ち、顔から血の気が引くのは、何かの強いショックやストレスを受けた時ですから、この歌詞に登場する女性の顔が蒼ざめたのは、the miller がtold his tale したから、つまりthe millerが彼女に何かを話したからだと僕は推測しました。そして、その瞬間、僕の脳裏を過ったのは、彼女の浮気相手(主人公の男性にとっては不誠実な嫌な存在)が彼女に「あいつ、俺たちの関係に気付いてるぞ」みたいなことを耳打ちしているような情景でした(因みに、前述のフィガロの結婚には、スザンナがそっと伯爵に手紙を渡し、その手紙のことを知ったフィガロが「どこかの色女が伯爵に恋文を渡したらしいぞ」と歌う場面が第3幕にあります)。浮気がばれたことを知って彼女の顔が蒼ざめた。それがこの第2節の僕なりの解釈です。そう考えると、次の節のthere is no reason and the truth is plain to see というのが「浮気に理由なんてないわ。見てのとおりよ」という彼女の開き直りの言葉に聞こえてきませんか?
分からないのはBut I wandered through my playing cards 以降の部分です。But I wandered through my playing cards は、開き直る彼女に対してどうすべきか悩んだと考えれば理解できますが、そのあとに続くAnd would not let her be one of sixteen vestal virgins who were leaving for the coast は意味不明としか言いようがありません。「vestal virgins?何ですかそれ?」状態でしたので、調べてみたところ、vestal virginsは古代ローマの火の神ウェスタに仕えていた巫女のことであることが分かりました。複数形になっているのは、ウェスタに仕える巫女の定員が6名だったからで、幼少期に巫女に選ばれた少女たちは、その後30年間、俗世から離れて処女でいることを誓わされていたようです。ここのone of sixteen vestal virgins を多くの方々は16人のウェスタの巫女の一人と和訳されているようですが、前述のとおり巫女の数は6人なので、僕はここのsixteen は年齢だと考えます。恐らく、この歌詞に出てくる彼女はそれくらいの年頃だったのでしょう。ウェスタの巫女になること=30年間も処女でいることを誓わされる、つまり、それは人生を棒に振るような行為の暗喩であり、不誠実な男のもとに走って人生を棒に振るような16歳の少女にはなって欲しくないというのが僕の解釈です。そのように理解すれば、それに続くAnd although my eyes were open. They might have just as well’ve been closed も、その思いはあくまでも彼の目から見た独善的なものであって、まだ若かった彼には現実が見えていなかったと解釈できるのではないでしょうか。最後の行のThey might have just as well’ve been closed は、なぜhave が重なっているのか良く分かりません。They might just as well have been closed でいいような気もしますし、実際、曲を聴いてみてもそう歌っているようにしか僕には聞こえませんでした。
シングルカットでは、このあとAnd so it was that later で始まるコーラス部分が2回繰り返されて曲はフェードアウトしますが、先に紹介した第3節は上記の僕の解釈を裏打ちしているようにも思えますので解説を続けたいと思います。She said, ‘I’m home on shore leave,’ Though in truth we were at sea. So I took her by the looking glass and forced her to agree というフレーズを聴いて僕の頭に浮かんだのは、彼女が浮気の言い訳をしている情景です。「昨日の夜、どこにいたんだよ?」「うちにいたわ」というやりとりのあと「嘘つくなよ。男と映画館にいたじゃないか。僕もあそこにいたんだぞ」と彼女に事実を認めさせようとしているみたいな感じですね(想像が飛躍し過ぎでしょうか・汗)。Saying, ‘You must be the mermaid who took Neptune for a ride.’はtake someone for a ride が人を欺くという意味ですから、mermaid は浮気した少女、Neptune は歌詞の主人公の少年であると理解しました。僕が思うに、mermaid は恐らくアンデルセンのThe Little Mermaid が念頭に置かれていて、アンデルセンの人魚姫は悲劇の主人公ですから、少年は「僕(Neptuneは海の神であり、少年自身は自らを彼女を守る存在と考えている)を裏切るなんて君は悲劇の娘(愚かな娘)だ」と浮気している少女を非難したのでしょう。ところが彼女の反応はshe smiled at me so sadly だったので、単なる浮気ではなく彼女が自分のもとを離れようとしていることに気付いてmy anger straightway diedとなったと考えればこの節の全てがきれいにまとまります。シングル版で削除された歌詞部分に関してKeith は「Our producer said, “Look, if you want to get airplay, if you want this record to be viable, you probably should think about taking out a verse.” And we did. I didn’t feel badly about it because it seemed to work fine. It didn’t really bother me」と発言していて、It didn’t really bother me という言葉から、削除された歌詞部分を彼はそれほど重要視していなかったことが窺えます。実際、最後の節に並ぶ言葉も意味不明なものばかりであまり重要ではなさそうですが、簡単に触れておきましょう。
1行目のIf music be the food of love は、シェイクスピアの戯曲からの引用であることは確定です。Twelfth Night, or What You Will の第1幕の冒頭でオシーノ公爵が口にする有名な台詞ですね。ここでシェイクスピアが引用されているが故にAs the miller told his tale もチョーサーの作品からの引用と考えてしまう人が多いのかもしれません。最初の2行と3、4行目では相反する事象が羅列され、そのあとMy mouth by then like cardboard seemed to slip straight through my head という言葉が続いています。僕が思ったのは、ここでのcardboard は段ボール紙と言うよりも実質のないものという意味であろうということであり、My mouth by then like cardboard を聴いて頭に浮かんだのは、陸にいる王子と会う為、言葉を話せなくなることと引き換えに両脚を得た(これもある意味、相反)人魚姫の姿でした。そのことがなぜにslip straight through my head したのかというと、何かを犠牲にして何かを得るということはないと主人公が気付いたからなのではないでしょうか。7行目のcrash-dive は、ずっと海に関係する話が続いていることから急いで海に潜るという意味であることに疑いの余地はありません(crash-dive だけでも潜水艦が急速潜航するという意味であるのにstraightway quickly と言葉が続いているのはtoo redundunt ですね。因みに海の話ばかり出てくるのは、Keithが海好きだったという単純な理由からのようです)。なので、So we crash-dived straightway quickly and attacked the ocean bed から僕が受けた印象は、今ならまだ間に合うとばかりに何か失ったものを過去(海底)に取返しに戻ろうとする姿でした。ただ、主語がI ならその理解でうまく辻褄が合うのですが、we(つまり、少年のもとを離れる決意をしている少女も含まれる)になっているので良く分かりません。ギブアップです!(笑)
ふーぅ。難解な歌詞の曲はやはり解説が長くなってしまいますね。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。Keith Reid が亡くなった今、この曲の歌詞の謎が解き明かされることはもう永遠に無いでしょうけど、最後にProcol Harum のリーダーであったGary Brooker(この方も2022年に死去)の言葉を記しておきます。
「I don’t give a damn what lyrics mean. You know, they sound great, that’s all they have to do.・ 歌詞の意味なんてどうでもいいのさ。音としてうまく響く、それが歌詞の役目なんだ」
本ホームぺージ内の『洋楽の棚』では100曲以上の洋楽の名曲を紹介していますので、興味のある方は覗いてみてください!